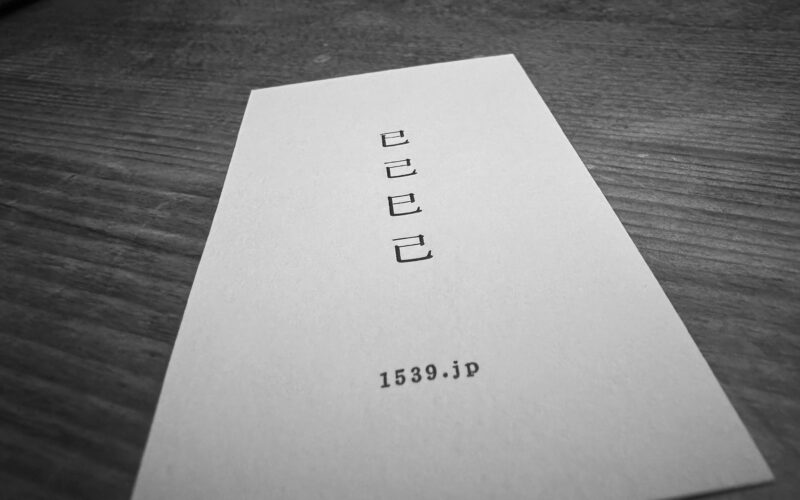※サムネイルの写真と本文は、全く関係ありません。
とある地方で、鉄道の利用者が壊滅的に減少していて廃線計画が浮上している。しかし、路線の通る自治体の首長連合は「活性化なら向き合うが廃線であれば話すら聞かない」と強硬姿勢であるという。たしかに、このエリアは、新幹線や高速などの整備もままならず、鉄道が廃線となればエリア全体に多大な影響を及ぼす(乗員がいないので及ぼさないと思うが)。
話を聞いてみると、路線のある首長や推進派の職員、ほぼ誰も鉄道を利用していないのだ。
鉄道会社側にも、沿線活性化を頑張る一団がいるので、彼らのその話をすると、なんと活性化を担当する側も乗っていない。
試しに電車に乗ってみると、しなびた駅舎で、電車待ちの高校生が牧歌的な風景を醸し出している。利用する側は何も考えず当たり前のように鉄道を使い、利用しない側は当たり前のように鉄道を使いもせず必要性を解いている。
岡目八目は、AI学会で数年前から盛り上がっている「認知」を語る上で、とても重要だと思うのだが、この件もまさに岡目八目的な指向性が生じている事例だ。
だから「乗客にアンケート」とか「駅でキャンペーン」などやったところで、利用者は必要すぎて何も見えてない対象者なわけだからうまくいくはずが無い。
かといって、自家用車主流の地方で、自家用車ユーザーに対して何らかの訴求をするというのは莫大なコストがかかるし、そもそも「自家用車より電車」と訴えるコンテンツが全く見えてこない。世界中の酒が飲める車両なども考えはしたが、二次交通が脆弱なため電車に降りたあとがついてこないのが地方の限界なのである。
そこで、電車を捨て「駅」というハコに着目してみた。路線全ての「駅」に関するGoogleマップのコメントをクローリングして分析してみると、一日数人しか乗降しない駅に、千を超えるコメントがあったりすることがわかった。
その内容を見ていると、サイクリストやバイカーが、1つのマイルストーンとして目指す目的地となっていることがわかってきた。風光明媚な名所は、裏返せば自然豊かで何も無いところでもある。
鉄道である。いざというときには電車がくる。人がいる。電気がある。屋根がある。駅とは、そういう場所だ。それであれば、その駅でしか買えない御当地シールやワッペン、その地域に暮らす有名人の手書きメッセージガチャなど、さいたま市の「与野ガチャ」のような自販機群。飲料や軽飲食の自販機群。それらが、売上を上げれば切符が売れない(人がいない地域)駅ほど、風光明媚で希少性がある場所としてお金が落ちる可能性がある。防犯・防災などの緊急時に向け、照明や防犯カメラなどを設置するのもありだろう。NFT化したデジタルスタンプとして、地域を超えて取引などがされるようになると販売した価格の数倍以上で取引されるコンテンツも出てくるかもしれない。人流データを元にした試算では、可能性レベルだが廃線検討ラインを上回るか同等くらいまでは戻せるかもしれないという結果も出た。
このアイデアは、やろうと思えばすぐにやってみることができるものだととても好評をいただいた。私は現場から離れるが、近いうち、そういった路線ができてくるかもしれない。
「鉄道=電車・乗客」というコンテキストを見直し、「駅舎の徹底活用」を主にする。もちろん、人がいないエリアなわけだから、実際に運用する上ではDXが必要となる。やはり、まずはコンテキストを見直したところにDXを添えるというのが正しいアプローチなのだと実感した取り組みだった。