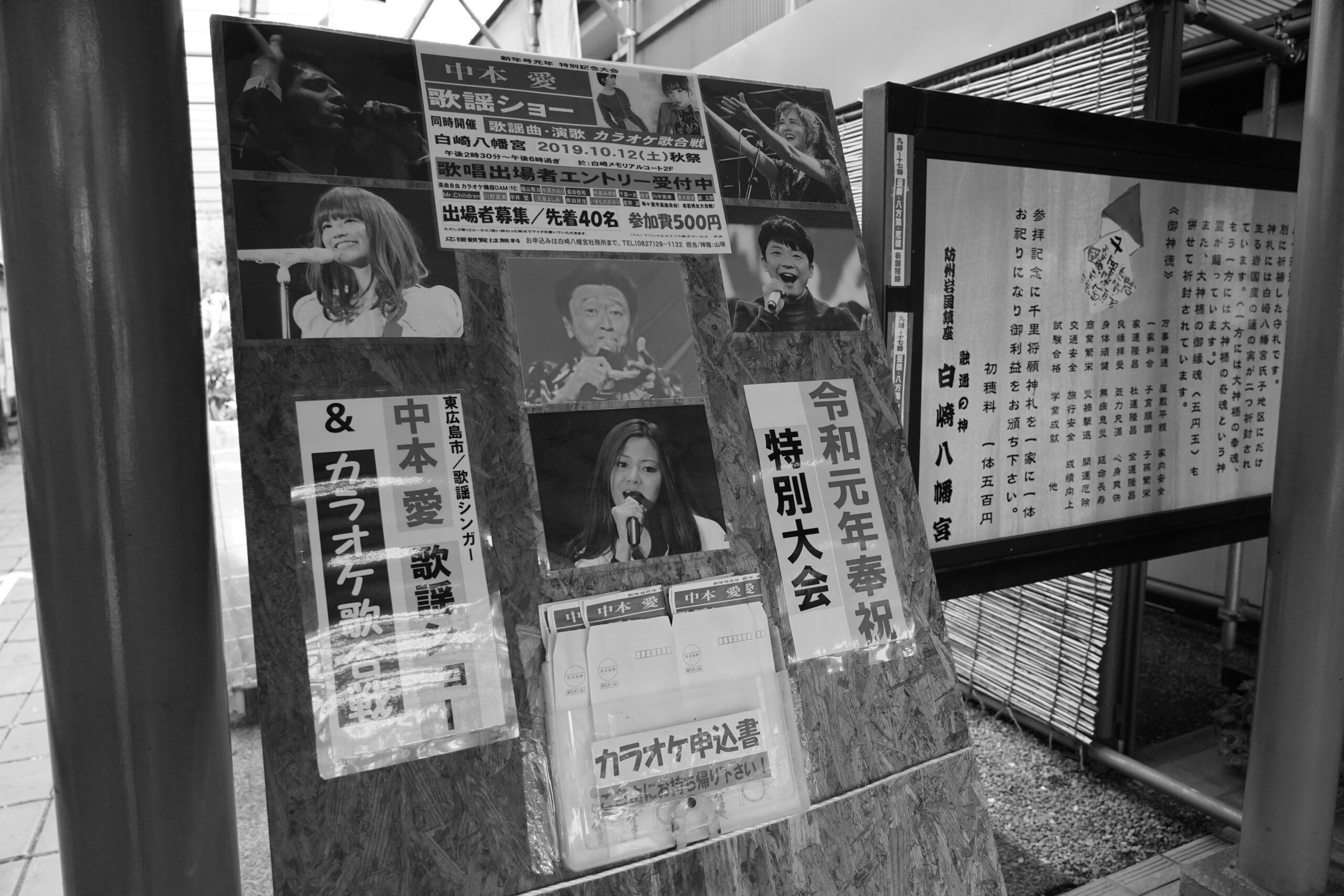※サムネイルの写真と本文は、全く関係ありません。
万年筆にハマっている。
インクがドバドバと出てくるし、書き心地もなめらか、まさに筆に書かされているという感じで、いくらでも長文が書ける。脳内をクレンジングするモーニングノートというのをやっているのだが、万年筆にしてからいくらでも書けてしまうので、睡眠も深くなってきた気がする。
そうなると、更に良い万年筆が欲しくなる。
ただ、高級な万年筆は金を使っているため、高くて躊躇していた。
たまたま、近所に文具屋を発見したのでなんの気無しに行ってみると、定価の半額以下の万年筆がズラッと並んでいた。金の値上げに合わせて定価がどんどん上がっているが、その店は仕入れた時の売価をそのままで販売しているという。
近所の文具屋で、そんな自分だけの発見・出会いをすると、その万年筆を殊更特別なものに感じる。
その文具屋は、とても汚く雑多な品揃えではあるが、聞けばSNSでバズることも多く、最近ではSNSを見た外国人が100人単位で店を訪れることもあるという。
もう1つ、以前から憧れていた万年筆が神戸にある。
ナガサワ文具センター。
神戸の各所をモチーフに様々なインクをつくり販売している。
それだけなら、画材店などでも良いのかもしれないが、ナガサワ文具センターは、そのオリジナルインクが映えるように透明な軸の万年筆をメーカーと共同開発し販売しているのだ。
プロフィットのスケルトン版、「プロスケ」。
センチュリーのスケルトン版、「センスケ」。
プロフェショナルギアのスケルトン版、「ギアスケ」。
漆をつかった伝統技巧満載で数百万する万年筆より、このインクを主に魅せるという粋なデザインと見える部分に施された金の配色が美しく、憧れの存在であった。
ただ、実用的な黒字と赤字万年筆はすでに持っていて不満もない。そこに、緑色や紫色のインクなど無駄の極みであるから、なかなか手が出ない。
仕事で神戸に行くたびに、ナガサワ文具センターのショーケースを見るだけ見て帰る日々。
ところが、とあるきっかけでナガサワ文具センターの役員と知り合い、万年筆を紹介いただき、特別価格で購入させていただけたのだ。
特別価格はもちろん嬉しいのだが、それよりも、自分が惚れたインクや万年筆を作ってきた関係者とその想いを共有し、憧れたものを手に入れたことも共有できたことがとても嬉しく、久々に興奮した日となった。
文具店は、今、Amazonなどに押され廃業が多いと聞く。
ただ、上記2つの文具店に共通しているのは「体験価値」なのだと思う。体験は、ECサイトでは難しい。
文具、店舗、イベント、ポップ、店員、全てがコンテンツであり、文具店はそれらを内包したメディアであると考えれば、まだまだ飛躍できる可能性があるのではと思う。
様々な文具を使ってみられる体験型施設として入場料を取る、ファンから毎月会費を徴収し希少な文具の優先購入イベントなどを主催する、同じ文具のファンを集めコミュニティ化する、などなど。
それら次世代型文具店は「行かなきゃどうにもならない」ものであるから、集客の重力場も強い。集客をしたい別事業主からテナント誘致を貰えるまでになれば、出店コストも下げられる。1箇所1箇所は、コーナー、くらいの大きさでも良いではないか。
こうやって文具店のコンテキストを再定義していくと、それを効率的・効果的に実現するために、手段としてのデジタル化も絡んでくる。これが、真のDXである。